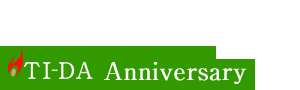2012年03月15日
住居の形② -歴史的経緯-
皆さん、おはようございます!
弥生3月も半ばに入ろうとしていますが、調子よくお過ごしでしょうか?
私はというと、なんだか少しのどが痛く「のど飴がほしい・・・」といったところです。風が冷たく空気が乾いているように感じるためなんだかのどがいがらっぽいです。
さて、「支え合ったら人になる、支えるから人なんだ、支え合うから人なんだ」という某団体から放送される唄からも感じられるとおり、人は一人で成立するのではなく、役割を分担し合い、励まし合い支え合い成立するものなのだと感じます。それは、動物に目を向けても、百獣の王ライオン、シマウマも集団を形成し、互いに役割を分担し合い、外敵に対する集団的抑止力を享受しておりますよね。集団の形成というのは、生物の本能のような気もします。
社会的集団の最小形態である家族が集い、共に生活を営んでいく「住まい」、その形は非常に様々な形があり得るのですが、ここから「集合住宅・マンション」というキーワードを軸に、住居の形態が集合住宅に至った経緯と、集合住宅にかかる法規制の経緯を俯瞰していきましょう。
まず、集合住宅が都市に住む者の住居形式として一般化していったのは、近代以降のことです。工業化社会の到来によって急激な都市化が進んだ当時、大都市の密集を拡散し労働者に経済的、衛生的な住宅を提供することは社会にとって最も急を要する課題の一つでした。日本においては集合住宅という形式がもたらされ、建設されだすのは大正末(1926年)から昭和の初め以降でした。その初期における集合住宅建設の先駆けとしては、関東大震災(1923年9月1日)後に設立された同潤会(詳細はhttp://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%90%8C%E6%BD%A4%E4%BC%9A(ウィキペディア同潤会)をご覧下さい。)の試みがあります。
戦後日本住宅公団が設立されると、その供給する住宅が雛形となって各地に団地が建ち並ぶようになります。集合住宅建設が本格化し始めるのです。その出発点と成ったのは、冬至四時間日照を基本条件とする平行配置というおそらく単純で貧しい論理でした。それが昭和30年代、つまり1955年ぐらいから公営・公団住宅において採用され、そのまま高度経済成長期を通じて日本の基本形をつくっていきます。
冬至の四時間日照、即ち冬至前後の日にも集合住宅に住む全ての人々に平等に日の光を保障し、良好な住環境を保障する。これが日本の集合住宅の平行配置と隣連との距離を設定するときの基本的な考え方だったのです。それは、確かに戦後都市住民にある一定水準の住居を提供することには成功しましたが、一方では固有性や地域性といったものが無視され、徹底的に画一的な住環境がつくりだされてきました。現在では、そのあり方も反省され、画一性を打破しようとするような試みがなされるようになってきましたが、いまだにその思想は日本の集合住宅における支配的な観念として根強く残っています。
ただ、そこには、経済の論理が最優先されていたことともう一つ、「持ち家一戸建て」にこだわり、特に南面に固執し続ける「日本人の住宅観」の問題が要因としてあるように思います。
日本では「南向き崇拝」とでもいうように、個人住宅、集合住宅に限らず部屋は全て南向きを良しとする傾向があります。そこには、人々の心の内にある日本の伝統的な住宅イメージが、根強く残っているような気がします。それは、おそらくかつての書院造りのような南側に庭があってそれを床の間からながめるといった性格のものです。
・・・と現代日本の集合住宅の伝統的構造に対し痛烈なコメントを発しています。
ここまでは、安藤忠雄氏に依って日本の個人住宅、集合住宅の歴史的経緯を見てきました。
それでは、その人が家庭が住まう「住宅」に対し、法はどのように制度設計され法的保護を設けてきたのでしょうか?
そして、どのような変遷を受け、現在どのような法的制約を設けているのでしょうか?
次回からは、住宅に対する法的規制の構造を俯瞰的に見ながら、諸処の視点から楽しみながら見ていきましょう。
それでは次回までこれにて失礼します。
参考図書:安藤忠雄「建築に夢を見た」日本放送出版会

夜の山形、先輩司法書士が人型を作ろうと積もる雪の中へダイブ。活気溢れる行動に思わずパシャ





弥生3月も半ばに入ろうとしていますが、調子よくお過ごしでしょうか?
私はというと、なんだか少しのどが痛く「のど飴がほしい・・・」といったところです。風が冷たく空気が乾いているように感じるためなんだかのどがいがらっぽいです。
さて、「支え合ったら人になる、支えるから人なんだ、支え合うから人なんだ」という某団体から放送される唄からも感じられるとおり、人は一人で成立するのではなく、役割を分担し合い、励まし合い支え合い成立するものなのだと感じます。それは、動物に目を向けても、百獣の王ライオン、シマウマも集団を形成し、互いに役割を分担し合い、外敵に対する集団的抑止力を享受しておりますよね。集団の形成というのは、生物の本能のような気もします。
社会的集団の最小形態である家族が集い、共に生活を営んでいく「住まい」、その形は非常に様々な形があり得るのですが、ここから「集合住宅・マンション」というキーワードを軸に、住居の形態が集合住宅に至った経緯と、集合住宅にかかる法規制の経緯を俯瞰していきましょう。
まず、集合住宅が都市に住む者の住居形式として一般化していったのは、近代以降のことです。工業化社会の到来によって急激な都市化が進んだ当時、大都市の密集を拡散し労働者に経済的、衛生的な住宅を提供することは社会にとって最も急を要する課題の一つでした。日本においては集合住宅という形式がもたらされ、建設されだすのは大正末(1926年)から昭和の初め以降でした。その初期における集合住宅建設の先駆けとしては、関東大震災(1923年9月1日)後に設立された同潤会(詳細はhttp://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%90%8C%E6%BD%A4%E4%BC%9A(ウィキペディア同潤会)をご覧下さい。)の試みがあります。
戦後日本住宅公団が設立されると、その供給する住宅が雛形となって各地に団地が建ち並ぶようになります。集合住宅建設が本格化し始めるのです。その出発点と成ったのは、冬至四時間日照を基本条件とする平行配置というおそらく単純で貧しい論理でした。それが昭和30年代、つまり1955年ぐらいから公営・公団住宅において採用され、そのまま高度経済成長期を通じて日本の基本形をつくっていきます。
冬至の四時間日照、即ち冬至前後の日にも集合住宅に住む全ての人々に平等に日の光を保障し、良好な住環境を保障する。これが日本の集合住宅の平行配置と隣連との距離を設定するときの基本的な考え方だったのです。それは、確かに戦後都市住民にある一定水準の住居を提供することには成功しましたが、一方では固有性や地域性といったものが無視され、徹底的に画一的な住環境がつくりだされてきました。現在では、そのあり方も反省され、画一性を打破しようとするような試みがなされるようになってきましたが、いまだにその思想は日本の集合住宅における支配的な観念として根強く残っています。
ただ、そこには、経済の論理が最優先されていたことともう一つ、「持ち家一戸建て」にこだわり、特に南面に固執し続ける「日本人の住宅観」の問題が要因としてあるように思います。
日本では「南向き崇拝」とでもいうように、個人住宅、集合住宅に限らず部屋は全て南向きを良しとする傾向があります。そこには、人々の心の内にある日本の伝統的な住宅イメージが、根強く残っているような気がします。それは、おそらくかつての書院造りのような南側に庭があってそれを床の間からながめるといった性格のものです。
・・・と現代日本の集合住宅の伝統的構造に対し痛烈なコメントを発しています。
ここまでは、安藤忠雄氏に依って日本の個人住宅、集合住宅の歴史的経緯を見てきました。
それでは、その人が家庭が住まう「住宅」に対し、法はどのように制度設計され法的保護を設けてきたのでしょうか?
そして、どのような変遷を受け、現在どのような法的制約を設けているのでしょうか?
次回からは、住宅に対する法的規制の構造を俯瞰的に見ながら、諸処の視点から楽しみながら見ていきましょう。
それでは次回までこれにて失礼します。
参考図書:安藤忠雄「建築に夢を見た」日本放送出版会

夜の山形、先輩司法書士が人型を作ろうと積もる雪の中へダイブ。活気溢れる行動に思わずパシャ






Posted by ひるとん at 09:36│Comments(0)
│法律